バスケットの上達には「運動神経」をどう育てるかがカギです。
- 実は、バスケの練習だけを頑張っても“運動神経”そのものは伸びにくい。
- 最新の研究では、水泳や体操など一見関係なさそうな種目が、
- バスケで必要な判断力や反応スピードの土台を作ることが分かっています。
「バスケットが上手くなるためにはバスケの練習だけではだめ。」
「バスケット以外のスポーツや遊びが多様な動作学習につながる。」
このような考え方は、スポーツ大国アメリカでは当たり前とされ、「マルチスポーツ」と呼ばれます。
「マルチスポーツ」で運動神経が伸びる理由とメリット
「マルチスポーツ」とは、1つの競技に特化せず、複数のスポーツを経験することを指します。
例:週のうちバスケ3日、水泳1日、休日に家族でキャッチボールやスキーを楽しむ、など。
幼少期から多様な動きを身につけた選手は、運動神経の基礎(バランス・リズム感・空間認知力)が高く、
結果的にメイン競技のスキル習得も早い傾向があります。
近年、日本でも、トップ選手が幼少期にバスケット以外のスポーツに取り組んできたエピソードが紹介される事が増え、マルチスポーツの重要性を耳にする機会は徐々に増えてきています。
運動や身体作り、そしてバスケットボールに携わる筆者としてはすごく嬉しく感じています。
しかし、マルチスポーツの重要性は理解されつつも、こんな声を聞く事もあります。
「バスケットのような判断を必要とするスポーツは、同じような球技としか関連しないのでは?」
「バスケットと体操は競技特性が違い過ぎる。バスケスキル向上には不向きでしょ?」
確かに、バスケットボールは相手や仲間の動きに瞬時に対応する「開放型スキルスポーツ」であり、判断力や反応の速さが求められます。
一方で、水泳や体操といった「閉鎖型スキルスポーツ」は、一定の環境で同じ動きを繰り返す種目。
「バスケの動きに直接つながらないのでは?」と感じるのも自然です。
しかし、最新の研究ではこんな結果が出ています。
バスケットボール選手と水泳選手の「記憶力」「集中力」「作業効率」といった認知機能を比べたところ大きな差はなく、両スポーツともに運動をしていない人より優れていた。
認知機能は、「開放型スキルスポーツ」においてとても重要な判断力の土台となる能力です。
興味深いのは、水泳のような閉鎖型スポーツでも、バスケットボール選手と同じように認知機能が高まっていた という点です。
つまり、
「認知機能を鍛えるのはバスケのような球技だけじゃない。水泳のような一見関係なさそうな種目でも効果がある」
ということが科学的に示されているのです。
本記事では、研究の大事な要点をお伝えするとともに、理学療法士・ミニバスコーチとして活動する立場から、バスケットの能力向上にどんな考えをもって他の競技や活動に取り組むべきかをお伝えします。
なぜ「運動神経」が良い子はバスケが上達するのか?
本記事は以下の論文の結果を参照して作成しています。
タイトル
Cognitive function and heart rate variability in open and closed skill sports
(オープンスキルスポーツとクローズドスキルスポーツにおける認知機能と心拍変動)
専門知識のない方でも内容を把握しやすいように、専門的な表現を出来るだけせずに記載しています。
原文を確認したい方は以下のリンクからご確認下さい。
↓↓
要約
目的
「開放技能スポーツ(open skill sports)/閉鎖技能スポーツ(closed skill sports)」という運動環境の違いが、選手の認知機能および心拍変動(Heart Rate Variability: HRV)にどのように影響するかを調べることを目的にしています。
方法
被験者を以下の3群に分けて比較しています:
- バスケットボール選手(開放技能スポーツ)
- 水泳選手(閉鎖技能スポーツ)
- 運動習慣のない座りがち群(非スポーツ群)
各群とも26名ずつ。HRVは PowerLab によって計測。
認知機能は以下のテストを実施:
- 認知機能は以下のテストを実施:
- Ebbinghaus Memory Procedure Test(EMT)
- Go/No-Go Task(GNG)
- Color Stroop Task
- Trail Making Test(TMT)
- Letter Cancellation Test(LCT)
結果
- 群間で多変量共分散分析(MANCOVA)を実施したところ、群間に有意な差が認められました。
- ただし、バスケットボール群と水泳群の間では、認知機能およびHRV測定値に有意差は認められませんでした。
- 両スポーツ群(開放/閉鎖いずれも)は、座りがち群(非スポーツ群)を上回るパフォーマンスを示しました。
結論
スポーツトレーニング(種目を問わず)は、総じて認知機能の向上に好影響を持つと結論付けられています。
つまり、どちらのタイプのスポーツ(開放技能/閉鎖技能)であっても「スポーツ経験あり」と「運動習慣なし」を比べると、認知機能が優れていたということです。
しかしながら、開放技能スポーツ群(バスケットボール)と閉鎖技能スポーツ群(スイミング)との間で、認知機能やHRVに有意な差は見られなかったため、「スポーツ種目の技能タイプが認知・HRVに異なるインパクトを持つか」については本研究では支持を得られなかったということになります。
【要点まとめ】
- ・運動している人は運動していない人より「集中力・記憶力・反応の速さ」が高い。
- ・バスケ(水泳)どちらも効果があり、運動の種類に関係なく脳を鍛える。
- ・特にVO2max(持久力)が高い人ほど、認知機能も良好。
- → つまり「運動=脳トレ」。水泳もバスケも、頭を使うスポーツになる。
全文を確認したい方はこちらをクリック
はじめに
スポーツは、環境が競技スキルに与える影響によって2種類に分類できる 。
予測不能で外的要因によってペースが決まる競技は 開放型スキルスポーツ と呼ばれる。
これには、バスケットボール、テニス、フェンシングなどが含まれる。
一方、比較的安定し自己主導的な環境で行われる競技は 閉鎖型スキルスポーツ とされ、陸上競技や水泳などがこれに当たる。
バスケットボールは開放型スキルスポーツの典型であり、選手は戦術的判断を行い、絶えず変化する試合状況に対応しながら相手チームのリングを攻めなければならない 。
これに対し、水泳は閉鎖型スキルスポーツに分類され、陸上競技と同様に安定した自己ペースの環境で行われる 。
このような競技環境の違いは、選手の認知能力に異なる要求を課す。
最近の系統的レビューによれば、現時点のエビデンスは、閉鎖型スキルスポーツに比べて開放型スキルスポーツの方が特定の認知機能を向上させる可能性が高いことを示唆している。
しかし、認知機能の特定領域における両者の影響の全容を明らかにするには、まだ十分なデータは揃っていない 。
この研究の方向性に沿って、本研究では、バスケットボール選手と水泳選手を比較し、運動習慣のない群との間で認知機能の違いを検討する。
また、Hillman らは、運動そのものや競技スポーツのトレーニングが認知機能や脳機能に有益な効果をもたらすことを報告している。
Bherer らの研究は、有酸素トレーニングによる心肺機能の改善が、高次の認知機能の向上をもたらすことを示している 。
本研究の目的は、バスケットボール選手と水泳選手、さらに非運動群を対象に、認知機能と心肺機能を調査・比較することである。
方法
本研究には、18〜30歳の78名が参加した。
被験者は以下の3群に分けられた。
- バスケットボール選手 26名
- 水泳選手 26名
- 非運動群(コントロール)26名
選択基準
- バスケットボール選手と水泳選手は、それぞれの競技に少なくとも週3時間、6か月以上継続して参加していること。
- 非運動群は、定期的なスポーツ活動を行っていない者とした。
除外基準
- 心血管疾患、糖尿病、既往の外傷、神経疾患、聴覚・視覚障害、喫煙歴を持つ者は除外した。
検査手順
身体活動量の評価後、参加者はまず認知機能テストを受け、その後に心拍変動(HRV)の測定を行った。
有酸素能力の評価(Aerobic fitness assessment)
体力レベルと最大酸素摂取量(VO2max)は Cooper 12分間走テスト によって評価。
このテストはKenneth H. Cooper博士が開発した方法で、参加者は12分間できるだけ速く、一定のペースで2点間を往復し、走行距離を記録する。走行距離に基づき、オリジナルの手順に従って推定VO2maxを算出した。
心拍変動の測定(HRV recording)
HRVは標準的なガイドライン に従い、Powerlabデータ収録システム(Powerlab 4/25 t, Chart v5.4 Pro, AD Instruments, NZ)を用いて記録・解析した。
- 被験者は静かな部屋で仰臥位をとり、12分間測定を行った。
認知機能テスト(Cognitive tests)
以下の課題を使用し、認知機能を評価
- エビングハウス記憶手続きテスト(EMT)
- Go/No-Go課題(GNG)
- カラーストループ課題
さらに、紙ベースで以下の課題を実施した。
- トレイルメイキングテスト(TMT)
- セット1:数字のみ(1〜25を順に結ぶ)
- セット2:数字とアルファベットを交互に結ぶ(1-A-2-B-3-C…)
- 手を離さずに最後まで行うよう指示し、所要時間とエラーを記録した。
- 文字抹消テスト(LCT)
- 960文字のうち25%をターゲット文字とし、参加者は鉛筆でターゲットを消去。
- 所要時間、誤り、見落としを記録した。
結果
身体的特徴の比較
- ANOVAによる群間比較の結果、身長 [F(2,75)=2.17, p=0.121]、体重 [F(2,75)=0.11, p=0.894]、BMI [F(2,75)=1.48, p=0.233] に有意差は認められなかった。
→ つまり、3群間で体格に大きな違いはなかった。
VO2max(最大酸素摂取量)
- 群間で有意差が認められた [F(2,75)=52.09, p<0.001]。
- 事後検定(Bonferroni)により、バスケットボール選手 (p<0.001) と水泳選手 (p<0.001) は非運動群よりも有意に高いVO2maxを示した。
- また、バスケットボール選手は水泳選手よりもVO2maxが有意に高かった (p=0.007)。
認知機能テストの分析(Analysis for cognitive tests)
- バスケットボール選手と水泳選手の間には有意差なし。
- 運動群(バスケ+水泳)は非運動群より有意に良い成績を示した。
具体的な違い
- LCT(文字抹消課題):
- バスケットボール選手は誤答が少なく (p<0.001)、非運動群より速く完了 (p=0.044)。
- 水泳選手も非運動群より速かった (p=0.002)。
- TMT(トレイルメイキング):
- バスケットボール選手 (p<0.001) と水泳選手 (p=0.002) は非運動群より速かった。
- EMT(記憶課題):
- バスケットボール選手は、非運動群より必要試行回数が少なく (p=0.013)、所要時間も短かった (p=0.026)。
心拍変動の分析(Analysis for HRV)
スポーツ種目の効果は有意ではなかった [F(20,128)=1.36, p=0.155]。
Spearman相関分析では、認知課題、VO2max、HRV指標の間に弱〜中程度の関連が示された。
まとめる
- 運動群(バスケットボール・水泳)は非運動群よりも認知課題の成績が良い。
- バスケットボール選手と水泳選手の間には認知機能・HRVで大きな差はない。
- ただしVO2maxではバスケットボール選手が最も高かった。
考察
本研究は、異なるスポーツタイプにおける心拍変動(HRV)と認知パフォーマンスを比較し、さらに非運動群との違いを評価することを目的とした。
先行研究に基づき、我々は「定期的なスポーツトレーニングは心肺持久力・HRV・認知能力を改善する」と仮定した。
その結果、仮説は支持され、定期的にスポーツ活動に参加している者は、持久力、持続的注意、ワーキングメモリ、実行機能において非運動者より優れていることが示された。
ただし、開放型と閉鎖型スキルスポーツ間では認知機能やHRVに有意差は認められなかった。
- ワーキングメモリ(EMT)
バスケットボール選手と水泳選手は非運動群よりも反応時間が速く、必要試行数が少なく、課題完了時間も短かった。
これはMoriyaらの研究と一致しており、中強度の運動が右前頭前野の活性化を高め、ワーキングメモリを改善することが報告されている 。 - 持続的注意(LCT)
両スポーツ群は非運動群よりも課題時間が短く、誤りも少なかった。
これは注意欠如障害や知的障害を持つ人において、運動が集中力や注意力を改善することを示した先行研究と一致する [。 - 実行機能(TMT)
両スポーツ群は非運動群よりも課題を速く完了した。
先行研究も、身体活動と実行機能の間に正の関連があることを示している 。 - 抑制制御(GNG・ストループ課題)
本研究ではスポーツ種目間で有意差は認められなかった。
運動習慣と認知機能を結びつける生物学的機序については多くの仮説がある。
・Colcombeらは、フィットネスが高い人は脳の灰白質と白質の量が多いと報告 している。
・Ericksonらは、フィットネスレベルの高さが海馬体積の増加と関連し、記憶力を改善することを示した 。
・Tsengらの研究でも、熟練アスリートは非運動者に比べて脳の灰白質・白質の量が多いことが確認されている 。
本研究では「開放型 vs 閉鎖型スキルスポーツ間の有意差」は認められなかった。
これは、Guoらの研究(視空間ワーキングメモリで非運動群よりスポーツ群が優れるが、開放型と閉鎖型間では差がない)と一致する 。
Beckerらの観察研究でも、2つのスポーツタイプ間で実行機能に大きな違いはなかった 。
また、Guらの系統的レビューでは、両者とも非運動群より認知機能に良い影響を与えるが、開放型が優れるという強い証拠は不足しているとされている。
まとめ
本研究は、定期的なスポーツ活動が認知課題の成績を改善することを確認した。
ただし、開放型スキルスポーツ(水泳)と閉鎖型スキルスポーツ(バスケットボール)の間で、認知機能やHRVに有意差はなかった。
→ 将来的には、縦断的研究により長期的な効果を解明する必要がある。
筆者の考察
記事冒頭で述べた疑問
「バスケットのような判断を必要とするスポーツは、同じような球技としか関連しないのでは?」
「バスケットと体操は競技特性が違い過ぎる。バスケスキル向上には不向きでしょ?」
に対する答えは、今回の研究結果を参考にすると、「NO」とはっきり言えるでしょう。
スポーツ活動において、認知・判断の機会を多く行う事は大切かもしれませんが、運動自体が脳の機能を向上させ、開放型スキルスポーツに必要な認知機能の向上にもつながる事が期待できます。
水泳や陸上競技、空手の型などのスポーツもバスケットを始めとした開放型スキルスポーツの向上に寄与すると思われます。
むしろ、お子さんの置かれている状況・環境次第では、サッカーやバレーなどの開放型スキルスポーツよりも水泳をおすすめ出来る事もあるくらいです。
その理由は以下の通り
- 認知機能向上と関連する心肺機能強化が期待できる
- 関節、荷重のかかる骨へのストレスが少ない
- 個人競技のため自分のペースで実施可能
研究論文でも触れられていたように、心肺機能と認知機能は相関しやすいそうです。
野球やバレーなどは持久系競技ではないため、長い走り込みや全力疾走の機会は少なく、心肺機能の向上には不向きです。
水泳は泳ぐ距離にもよりますが、息を止めながら全身運動を行うため、高い心肺機能が要求される競技です。
また、バスケットは激しいダッシュ、ジャンプの多い競技のため関節・骨にかかる負担はかなり大きい競技です。
他の研究によると、専門的に行っているスポーツの週あたりの時間>年齢になると、障害発生のリスクが増加するそうです。
(以下の記事ではさらに詳しく解説しています。)
↓↓
【ミニバス】これって練習のしすぎ?頻度はどれくらいが適切?対策は?

練習量の多いバスケットチームに所属し、かつ、サッカーや陸上競技(特に中距離種目など)を選択してしまうと、身体に負担がかかり過ぎてしまうかもしれません。
逆に、練習量が少なく、週当たりの練習時間が年齢に達しないのであれば、これら走る競技と併用しても問題はないかもしれません。
また、団体競技か個人競技かも大きなポイント。
サブで選ぶスポーツは、スクールなどのいわゆる「習い事」として実施する事が多くなると思います。
しかし、習い事でも、大会や試合などが開催される事が珍しくありません。
子供は当然、真剣に向き合っているため大会が近づくと、
「優勝するために、学校が終わったらみんなで集まって練習しよう!」
「この大会は○○も来れるよね??」
となるかもしれません。
「いや、おれのメインはあくまでバスケだから・・・」とはなかなか子供ながら言いにくいものです。
その点は、個人競技の水泳は心配なく行えると言えます。
ここで誤解していただきたくないのは、サッカーやバレーなどの団体競技が「バスケにとって意味がない」というわけではありません。
団体競技は「チームワーク」や「状況判断」「コミュニケーション能力」といった、バスケットボールに直結するスキルを養う場でもあります。
マルチスポーツのメリットを解説した他の記事では、他のスポーツがバスケットとどのようにつながるかを解説していますので気になる方は参考にしてみて下さい。
↓↓
【バスケ】NBA選手は競技特化が遅い!?マルチスポーツのメリットとは?

お子さんの興味や得意・不得意。周りの仲の良い友達によって選択は変わります。
選択に正解はありません。お子さんとよく話し合ってどのスポーツがベストかを探してみて下さい。
バスケ+水泳 → 持久力・心肺機能・集中力アップ
バスケ+体操 → バランス・空中感覚・転倒防止
バスケ+陸上(短距離)→ 加速力・ジャンプ力
バスケ+スキー/スノボ → 下半身強化・体幹安定
遊び(鬼ごっこ・公園遊び)→ 反応スピード・方向転換力
他のスポーツができない子はとにかく遊び時間を増やそう
ここまで、バスケットが上手くなるために、複数スポーツを行う事を推奨して来ました。
マルチスポーツには多くのメリットがある事が研究によっても謳われるようになっていますが、住んでいる地域や家庭の事情などで、現実的には難しいご家庭もあると思います。
そんな、方におすすめしたい事はとにかく「遊ぶ」事です。
運動によって、認知機能が高まる事は前述しましたが、運動だけでなく遊びの中でも、バスケットに必要な認知機能は高まります。
バスケット以外の運動を行う事が難しい方は、是非以下の記事を参考にしてみて下さい。
↓↓
【バスケ】センスがある子の秘密 バスケ選手に必要な”AIQ”とは?
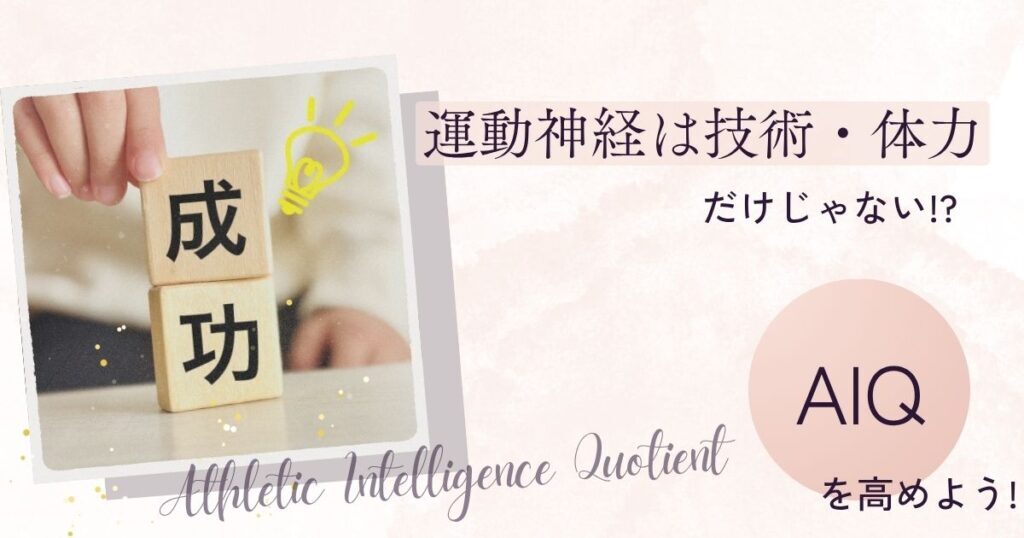
まとめ|運動神経を育てるとバスケがもっと上手く・もっと楽しくなる
本記事では「水泳がバスケットの補完スポーツとして有効」という研究を紹介しました。
もちろん、サッカーやバレーなどの団体競技もバスケット上達に役立ちます。
ただ、心肺機能を鍛えつつ、関節への負担が少なく、自分のペースで続けられる という点で、水泳はおすすめできる選択肢です。
バスケが上達する子ほど、実は“バスケ以外”でもよく動いています。
今日からできることは、“練習以外の運動を1つ足す”こと。
週1回の水泳、放課後の鬼ごっこ、公園でのボール遊びでもOK。
それらがすべて「運動神経の引き出し」を増やし、試合での判断力につながります。
日本においてまだまだ浸透していないマルチスポーツを実践していくのは簡単ではありません。
しかし、多くの国でメリットがある事がある事が知られているように、日本でも昔に比べて理解してもらえるようになりつつあります。
筆者が知る限り、まだまだマルチスポーツの情報をは多くありません。
書籍も少ないですが、以下の本はマルチスポーツの有用性をわかりやすく解説されいます。
↓↓
保護者の方も一緒に相談しながら、お子さんに合ったスポーツを選んでみてください。




コメント