「うちの子、足は速いけどドリブルのスピードはイマイチ・・」
「速攻でドリブルして行っても追いつかれてしまい、レイアップにいけない。」
そんな悩みを持つ保護者・コーチも多いのではないでしょうか?
ドリブルを上手くするためにはとにかく練習が必要です。
しかし、直線を走るためのスピードドリブルを速くするためには、ただ練習するだけではなく正しいフォームで行うことが重要です。
ブラジルとオランダの研究チームが、
バスケットボールの“スピードドリブル”を科学的に分析し、
専門家が認めたチェックリストを開発しました。
この研究では、
「速さ」ではなく「動きの質」に注目しています。
その結果、「上手い子がやっている9つの共通動作」が明らかになりました。
以下から、研究内容とチェックリストをご紹介します。
試合でもレイアップで簡単に得点できる選手を目指したい方は、チェックポイントを確認してみて下さい。
スピードドリブルのチェックポイントを示した研究
以下から実際の研究を訳したものをご紹介します。
原文を確認したい方は以下から
↓↓
要約
この研究の目的は、バスケットボールの「ストレートスピードドリブル」技能の熟練度を評価するためのチェックリストを開発し、その妥当性と信頼性を確認することでした。
対象は、7〜15歳の子ども100名(バスケットボールの練習経験がある者とない者を含む)。
開発したチェックリストは、ドリブル動作を構成する9つの要素からなり、動作の質(プロセス)に注目して評価を行いました。

このチェックリストが本当に使えるものかどうかを確かめるために、研究チームは次のようなテストを行いました。
専門家の意見を聞く(内容の確かさ)
→「この項目はドリブルの上手さを見るのに正しいですか?」と、熟練したバスケット指導者3名に確認。
上手い子とそうでない子を正しく見分けられるかを調べる(分類の正しさ)
→ チェックリストで判定した結果が、実際のレベルと合っているかを比較。
同じ人を何回見ても結果が同じかどうかを見る(結果の安定性)
→ 評価する人が変わっても、同じ結果になるかを確認。
練習の前後で変化をちゃんと測れるかを確認する(変化に気づける力)
→ 練習した子が上達したとき、ちゃんと点数が上がるかをチェック。
その結果、
- チェックリストの各項目はスピードドリブル技能の本質を的確に表していること、
- 異なる熟練レベルの選手を明確に区別できること、
- 評価者間・同一評価者間の一致度が高い(客観性が高い)こと、
が確認されました。
この研究により、開発されたチェックリストは、
スピードドリブルの学習過程や上達度を信頼性高く分析できるツールであることが示されました。

詳しい研究内容を確認したい方はここをクリック
方法
テスト内容
被験者は18mの直線コースを、できるだけ速くドリブルしながら走る課題を実施。
好みの手でボールをつき、途中で止まる必要はなし(ゴール後も走り抜け可)。
動作はビデオで記録され、後に分析(ソフト:Kinovea 0.8)。
チェックリストの開発
- 第1版:文献(Cousy & Power, 1975; Ferreira & Dante, 2003)を基に5項目を作成
- パイロットテストで感度不足が判明 → 8項目を追加(第2版)
- バスケット専門家3名による内容妥当性評価を経て、不要項目を削除し、新たに「全行程でボールコントロールできているか」を追加
- 最終版は9項目(第3版)に確定

結果(Results)
内容妥当性(Domain Validity)
評価者の86%が「5(非常に同意)」を選択。
→ チェックリストはスピードドリブルの主要要素を網羅。
判定妥当性(Decision Validity)
φ平均値=0.85 ± 0.05(高い一致率)。
信頼性・客観性
- 評価者内一致(intra-rater):κ=0.82
- 評価者間一致(inter-rater):κ=0.77
- 再検査信頼性:κ=0.77
→ いずれも「高い一致度」。
反応性(Responsiveness)
10回のドリブル練習後、成績が有意に向上(p < .01)。
→ 練習による技能向上を検出可能。
動作プロセスと成果(タイム)の関連
プロセス得点とタイムに強い相関あり(r=−0.72〜−0.65)。
考察(Discussion)
このチェックリストは**プロセス評価(動作の質)**に焦点を当て、
単なる「タイム」や「結果」では見えない運動要素(姿勢・滞空期・視線など)を定量化できる。
若年群で「視線が下がる(C7)」傾向が多く、未熟者はボールを見て操作する視覚依存が強い。
→ 練習により触覚情報への依存が増し、自然に頭を上げられるようになる。
教師・コーチがどの要素が改善を妨げているか(例:ボールを体の前でつくなど)を特定し、
指導内容を修正するのに有用。
ビデオ分析を用いる点は手間がかかるが、誤判定を防ぎ、
高い再現性を確保できる。
結論(Conclusion)
このチェックリストは、
- スピードドリブル技能の熟練度評価に信頼して使用でき、
- 学習・発達の過程を分析・指導に応用可能なツールである。
教育現場(体育授業)やコーチング、研究用途において、
プロセス評価に基づく技能向上のモニタリングが期待される。
筆者の考察
チェエクリストが有効なのはわかったけど、なぜこのフォームがいいの??」と思う方もいるのではないでしょうか?
以下からは筆者の考察ですが、チェックリストの内容を細かく分析し、
なぜ、その要素が大事なのか?修正の方法はどうするか?を深掘りします。
跳ねるように走る=「床反力」を使える選手
チェックリストの1番は「滞空期がある」でした。
滞空期があるとういうことは、軽く跳ぶ・跳ねるように走っている選手です。
つまり「軽く跳ねるように走る」選手は、床をしっかり押して反発をもらう動きができています。
(これを「床反力」と言います。)
跳ねるように地面を押すと、走るエネルギーが前に伝わり、スピードに乗れます。
逆にベタ足で走ると、この反発力をもらえず、スピードが落ちます。
足が速い選手は脚力が強い。と思われがちですが、実はそれだけではなく、床反力を上手に利用する事で速く走る選手もいます。
もっと詳しく知りたい方は以下のリンクから
↓↓
【バスケ】筋肉だけじゃない!瞬発力のある選手はこんな練習をする!

振り脚を90°に曲げる=すぐにお尻で蹴り出せる
振り脚を90°に曲げることを推奨するのは、着地後に素早くお尻の力を発揮して地面を蹴る事でできるからです。
膝が90°に曲がった状態で着地すると、下の画像のように体の重心がすでにお尻(股関節)〜ハムストリングの真上にあります。

そのため、
- 着地した瞬間にお尻の筋肉で体を受け止められる
- 支持期(片足で支える時間)が短くなる
- すぐにお尻の力で地面を押し返して「次の一歩」へ移れる
→ つまり、“接地から蹴り出しまでの時間(接地時間)”が短くなる事が期待できます。
一方、以下の写真のように脚が伸びたまま着地するとどうでしょうか。

- 接地位置が体より前になる
- 重心がまだ後ろにある状態で接地してしまう
- 結果、体重を乗せる→沈む→押すという3段階が必要になる
つまり、時間ロスが大きくなり、スピードは落ちます。
踵で着地する事で選択の幅は広がる
優秀な陸上短距離選手(スプリンター)手は皆、つま先~母趾球付近での接地(フォアフット)すると言われています。
しかし、今回の研究で推奨されるのは踵での接地です。
速く前に進むためには、つま先で接地した方が有利なはずなのに、なぜ踵が推奨されるのか??
この矛盾を考えていきます。
スプリンターの走り方は、まっすぐ前だけに進むことに特化しています。つま先接地する事で
- 接地時間を最小限にする(0.09秒以下)
- 地面反力を縦方向ではなく「斜め前上」に効率よく使う
- 関節の“たわみ”を減らして推進力を逃さない
事が期待でき、効率よく、速く前に進むためには有利です。
しかし、この接地の仕方は方向転換・減速には不向きです。
バスケットボールは前進だけでなく、停止・方向転換・後退 など動きも重要です。
つま先接地でスピードに乗った体を急ストップしようとするのは難しく、ふくらはぎの筋肉には非常に強い負荷がかかります。
つま先接地の走り方は、接地後の選択が「前進」しかありません。
スピードのみをチェックしたテストとはいえ、バスケットのスキルとして活かすには踵接地でのスピードドリブルが良いと判定されたものと筆者は考えます。
「体幹の前傾」を作るには「お尻の筋肉」がカギ
研究では、上手なドリブラーほど「体幹を15〜25度前に傾けている」ことがわかりました。
この姿勢は、速く動くための片脚“パワーポジション”とも言えます。
体幹を前に傾けるためには、腰から折れるのではなく、股関節を曲げて姿勢を作る必要があります。
そのためには、お尻(大殿筋)や太ももの裏(ハムストリングス)がしっかり働くことが重要です。
別記事では、理学療法士である筆者が医療・スポーツ現場で指導してきた、正しいパワーポジションの取り方をまとめています。
・体幹の前傾ができず、背中が丸まる
・腰がそってします
・膝が内側に入る
・腰を長く落としていられない
などパワーポジションが上手く取れない選手は山ほどいます。
そんな方は以下の記事を参考になぜ出来ないのか?を探してみて下さい。
↓↓
>>バスケ上達の鍵。「パワーポジションがとれない」は理学療法士が解決

前を向く・ボールを失わないには「反復練習」
研究では、上手な選手ほど「頭を上げて前を見ている」「ボールをコントロールできている」ことも分かりました。
ドリブルを上手につけるようになるためには、当然ですがドリブル練習を反復して行う事は必須です。
チーム練習の中でドリブルを集中的に練習する時間は意外と短い場合が多く、自宅での練習は欠かせません。
フォームには問題がないけど、ボールのコントロールがまだまだ・・。という方は、後は練習あるのみです。
以下のリンクから内容を確認して、優秀なドリブラーになる第一歩を踏み出してみて下さい。
↓↓
また、別の記事ではドリブル以外にもが行える自宅道具を紹介をしています。
ドリブル以外にも自主練方法に困っている方は是非参考にして下さい。
↓↓
【初心者〜中級者向け】バスケスキルを自宅で伸ばす練習・厳選道具紹介
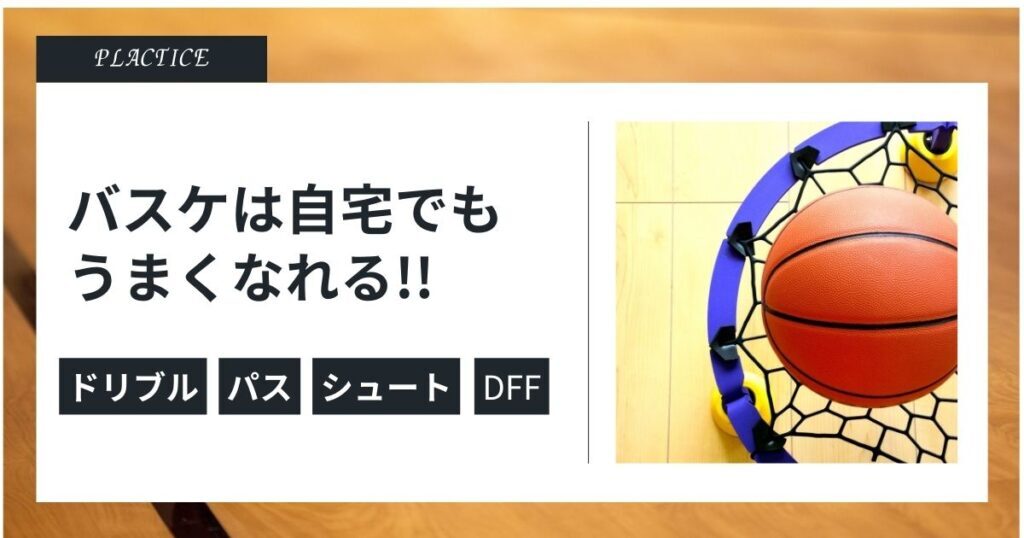
まとめ
足が速いのにドリブルになると追いつかれてしまう。
その原因は“筋力不足”だけではなく、“フォームの”も重要です。
ブラジルとオランダの研究で明らかになったのは、
「上手い子の動きには9つの共通点がある」ということ。
それは、ただボールをつくのではなく、体の使い方そのものが違うということです。
滞空期を作る、膝を90°に曲げる、踵で接地する、体幹を前傾させる――
こうした小さな動作の積み重ねが、結果的に「速く・強く・コントロールされたドリブル」へとつながります。
ドリブルを速くするために必要なのは「才能」ではなく「正しい理解と練習」です。
フォームのポイントを知り、自分の動きを少しずつ整えていくことで、
誰でも“スピードに乗ったドリブル”を身につけることができます。
最初は難しく感じても大丈夫。
「頭を上げる」「軽く跳ねる」「お尻で蹴る」など、1つずつ意識するだけで必ず変わります。
自宅でもできる練習器具を使えば、限られた時間でも質の高いトレーニングが可能です。
正しい方向で努力を続け、
「追いつかれないドリブラー」を目指してみて下さい。





コメント